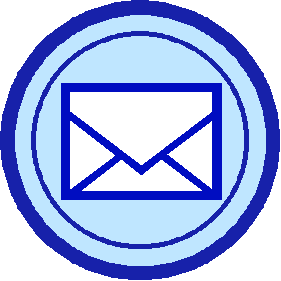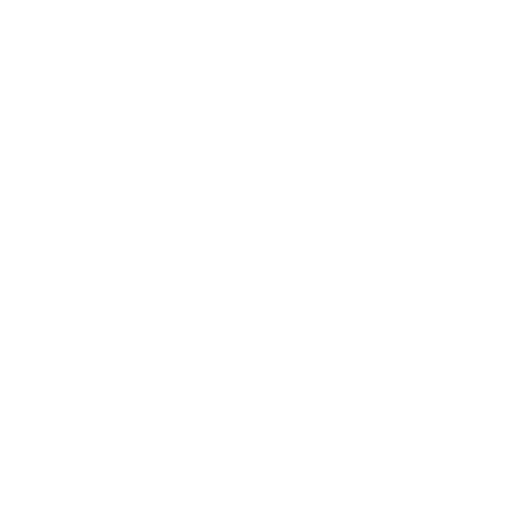中心性頚髄損傷による12級後遺障害残存を否認した地裁判決紹介
○交通事故被害者が中心性頚髄損傷により12級相当後遺障害が残ったとして約1290万円の損害賠償請求をして、被告保険会社側では中心性頚髄損傷を否認し、後遺障害は存在しないと厳しく争い、顧問医師の意見書や原告本人の生活状況についての写真入り報告書等を証拠提出しました。
○これについて12級後遺障害を否認し、14級後遺障害を認定し、約11万円の損害を認めた令和6年3月8日名古屋地裁判決(自保ジャーナル2174号26頁)の関連部分を紹介します。原告本人の介助無しでは歩けない、右手は使えない等の本人質問供述について、記憶違いや勘違い等では済まされないものであり,まことに遺憾ではあるが,原告が実情よりも自身の症状を重く見せかけ(宣誓の上で供述をしたものであるが,法廷での一部の供述は信用性に欠けるものといわざるを得ない。),より多額の賠償を得ようなどとしているものと見ざるを得ないと、極めて厳しい判断がなされています。
********************************************
主 文
1 被告は,原告に対し,11万3800円及びこれに対する平成30年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 請求
被告は,原告に対し,1289万4797円及びこれに対する平成30年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
本件は,原告が,原告運転に係る自家用普通乗用自動車(以下「原告車」という。)と被告運転に係る自家用普通乗用自動車(以下「被告車」という。)が衝突する交通事故が発生し,原告が傷害を負うなどの人的損害を被ったとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき,1289万4797円及びこれに対する上記交通事故の日(不法行為の日)である平成30年7月31日から支払済みまでの民法(利率につき,平成29年法律第55号による改正前の民法)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお,被告が原告に対して提起した本件本訴(当庁交通事故による損害賠償債務不存在確認請求事件)は,取下げにより終了した。
1 争いのない事実等
(中略)
第三 争点に対する判断
1 過失相殺の可否・割合
(中略)
2 原告の損害の内容
【認定事実】
関係証拠及び弁論の全趣旨によれば,これまでに認定した事実に加え,次の事実が認められる。
(中略)
(10)
ア 調査報告書,には,要旨,原告が,令和元年6月28日において,介助なく(誰かと腕を組んだりせずに)歩行する様子,両手で(カートの一部を抱え込むようなことはなく)荷物の入ったカートを押す様子,右手で「f」(500ミリリットル程度の液体が入ったペットボトル様の商品)を持ち上げる様子,同月30日において,右手で弁当を持ち上げてかごに入れる様子,介助なく段差を上る様子,右手で家の鍵を開ける様子などを撮影した写真が添付されている。
イ 調査結果報告書には,要旨,原告が,令和4年7月19日において,介助なく歩行する様子,首を一定程度左に回して左を向くなどの様子,同月30日において,右手で車両のドアを開けて左手でスマートフォン(電話)を耳に当てて使用する様子などを撮影した写真が添付されている。
ウ 証拠調べの後日に提出された動画については,上記調査報告書等に添付された写真に係る映像,すなわち,原告が,令和元年6月28日において,介助なしで歩行できている様子(特に歩行に違和感はないが,印象としては,ややゆっくりめではある。),カートの持ち手を右手と左手で握って,カートを押して歩く様子,fを右手の手指でつかみ,かごに入れる様子,右手で商品を棚から取る様子,同月30日において,上記同様にカートを押し,右手で商品を持ったりしている様子(特段ぎこちない様子はない。),夫と腕を組んで歩く様子,介助なく(腕を組まずに)歩行し,段差を上がり,右手で玄関の鍵を開けるなどして自宅に入る様子,令和4年7月19日において,介助なく歩き,夫の運転する車に乗り込むなどの様子(カラーは装着していない),同月30日において,夫と腕を組んで歩いたり,介助なく歩いたり,カートを押したり,右手でビニール袋ないし鞄様のものを持ちあげたり,左手でスマートフォン(電話)を持って通話をしつつ右手で自動車のドアを開けて,通話したまま自動車に乗り込んだり,右手で鞄様のものをもって左手で自動車のドアを開けて自動車に乗り込んだりしている様子(この日もカラーは装着していない)等が撮影されている。その様子を一部抜粋するに,別紙2の写真3及び写真4のとおりである。
(11)原告は,本件事故の前はe会社に勤務していた。原告の平成29年の収入は151万1,310円である。原告は,本件事故後は稼働していない。
(12)原告車の同乗者3名は,いずれも特に負傷しなかった。
(中略)
【検討・判断】
上記認定事実を踏まえ,各損害費目について判断を示す(なお,金額等については,本項において関係証拠に基づき認定する。)。
(中略)
(5)後遺障害逸失利益 85万9873円
ア
(ア)まず,原告の後遺障害の有無・内容について検討する。
原告は,本件交通事故後,両上肢のしびれ,頸部痛,頭痛,右肩痛,左肩痛を訴えており(これが継続的な訴えであったかについては,疑義なしとし得ないが,たとえば証拠(略)の診断書には,これらの症状の部位が図示されている。),後遺障害診断書によれば症状固定時においてもこれらの症状が残存していること,頸部については,Dの意見書においても,頸部の神経症状が残存したものと説明可能とされていることなどから,これらはいずれも少なくとも14級9号に該当する後遺障害と評価できるものと判断する(頸部痛・頭痛は一括評価されるべきものであり,3ヶ所に係る併合14級ということとなる。)。さらに,頸部痛・頭痛を12級相当の後遺障害と評価すべきかや,両上肢のしびれについては,中心性頸髄損傷との関係で検討すべきものであると解されるので,後述する。
この点,被告は,原告の主訴が信用できないことなどを指摘し,14級相当のものを含め後遺障害の残存を否定するが,本件事故態様や,上記調査報告書等における原告の動静に照らしても(その所作は,一定の神経症状を有している者のそれと見て矛盾はしない。),原告の主訴がすべて虚偽であるとはおよそ考え難いことなどに照らし,採用できない。
(イ)次に,原告の頸部痛や両上肢のしびれ等が,本件事故による中心性頸髄損傷に起因するものか(医学的・他覚的所見によって裏付けられるものか)について検討する。
まず,原告は,医療センターにおいて中心性頸髄損傷と診断されているところ,その診断書には「XPにより中心性脊髄損傷を認めた。」とある。ところが,被告側の意見書の内容(この点,自賠責保険に係る手続経過をみても,一貫して画像所見の存在は否定されている)等に照らすと,本件がXPにより中心性頸髄損傷が発生したと判断できる事案とは考え難い(もとより,一定の傷病名を付した上でその後の治療に当たる診療医の診断と裁判手続きにおける認定とでは,性質が異なる面があろうが,画像の見方については,直ちに医療センターの医師の見解に依拠することはできない。)。
このように,少なくともXPを根拠とした中心性頸髄損傷の診断には一定の疑義があるといわざるを得ないのであり,これにより中心性頸髄損傷の発症が立証できているとはいえない。なお,b整形外科における診断(後遺障害診断を含む)についても,「医療センターの専門医がそう判断している」ことに相当程度依拠しているものであって,やはり十分な根拠(他覚的所見)を有する診断とはいえない。
そして,神経学的所見についても,スパーリングテスト等はされているが,これは原告の主訴が影響する検査手法であるし(もとより,これのみでは直ちに他覚的所見が存在するとは評価できない性質の検査手法と解される。),握力測定については,後述の原告の主訴の疑わしさに照らし,その正確性に一定の疑義があるなどの問題がある上,治療経過に照らしても症状の一貫性や改善可能性がないことなどが示されているとは評価し難い。
そして,原告の主訴・症状等の訴えについては,相当程度の疑いがあることを指摘せざるを得ない。たとえば,典型的なものを挙げると,原告は,本人尋問において,介助(付添人と腕を組むなど)なしでは歩けない,右手で物を持てない(軽いスプーンなどは除く)などと述べたが,明らかに虚偽である。その他にも,できることをできないと言ったり,症状を実際よりも重く見せようという供述部分が多々ある。
これらの多くは,記憶違いや勘違い等では済まされないものであり,まことに遺憾ではあるが,原告が実情よりも自身の症状を重く見せかけ(宣誓の上で供述をしたものであるが,法廷での一部の供述は信用性に欠けるものといわざるを得ない。),より多額の賠償を得ようなどとしているものと見ざるを得ない。
なお,原告の状態に関する証人C(※原告の娘)の供述についても、原告と意を通じて虚偽又は誇張に係る供述をしているか,少なくとも原告の状況を正確に把握した上での供述でないことは明らかであって,その証拠価値は限定的である。
そうすると,少なくとも本件訴訟における陳述書や証拠調べに係る原告側の供述の信用性はかなり慎重に検討しなくてはならないし,特に後遺障害診断書の作成ないしその認定手続(異議申立てを行って,正当な等級認定を追及すること自体にまったく問題はないが,上記のような供述態度も考慮すると,当時において原告が相応の賠償志向を有しており,誇張した主訴を訴えたり,医師にそうした内容の診断書の作成等を暗にでも求めた可能性は否定し難い。)に係る医療的資料の内容についても,裁判上の立証の有無を検討するにあたっては,一定の懐疑的視点をさしはさむ必要がある。
付言するに,医療機関のカルテを見ると,最終的に後遺障害診断書に顕れた比較的重い神経症状が,治療期間中に継続していたようには必ずしも読み取れないという問題もあるところ,本件のように,後遺障害診断書の作成や異議手続等の段階で,それまでの診療記録からは必ずしもうかがわれない症状経過が示されたり,主張されたりする場合(たとえば,b整形外科の後遺障害診断書によれば,頸部痛,頭痛,両肩痛は初診時より絶えず存在,両上肢のしびれも絶えず存在,とされるが,診察期間中のカルテには,たとえば,右上肢と右手はしびれ痛ありなどとされながら,左上肢のしびれが指摘されていなかったり,「今朝から」左上肢に痛みと痺れが走り,などの記載もあるし,運動を実施,調子は良くなってきている,点滴後問題なしの記載が散見される反面,頸部痛や頭痛が絶えず存在していることを示唆するような記載は見受けられない。)については,後遺障害診断書の内容等が診療記録と内容的に十分一致又は整合している場合に比して,その信ぴょう性について慎重に検討しなくてはならないし,本件のように患者の賠償志向が見て取れる事案においてはなおさらである。
もっとも,医師は,患者の訴えに沿う診療を行うものであるから,虚偽又は誇張された主訴を医師が信頼し,又は医師において患者の要請に応えようがために一定の配慮をしたような診断書等が後遺障害認定手続等に至って作成される場合はあり,そのこと自体が直ちに問題視されるべきではないかもしれないが,少なくとも,被告の賠償責任の有無・範囲を画するべき裁判所としては,上記のような懸念・問題意識をもって所要の検討をせざるを得ない。
そして,こうした主訴に関する疑いは,ひいては,本件で指摘されているスパーリングテストや筋力・握力測定等の,神経学的所見の正確性に相応の疑問を生じさせるものといわざるを得ない。
こうした検討を踏まえて,改めて原告の後遺障害を立証すべき証拠について検討するに,たとえば,後遺障害診断書に係る「脊髄症状判定用」については,原告がスプーン,フォークも使用不能(右手)という状況にあるとは認めがたい(その状況で症状が固定したなどとは到底認められない。)などの問題があるし,紛争処理機構も,「本件事故翌日に左手を中心に痛みが増し,両手も動かしにくくなってきた」「翌々日,右手は痛みによりほとんど動かすことができなくなった」などの,医療記録に照らして認め難く,又は誇張されている可能性がある原告の訴えを前提に,前述のとおり信ぴょう性について慎重に検討すべき神経学的所見に係る医証を前提として(この手続では,自賠責保険会社等から新たな意見陳述書等の提出はなかったようであり,調査報告書等は判断の前提となっていないため,やむを得ないことではあるが。)判断がされたがために,十分な説得力を有しない内容になっているといわざるを得ない。
かえって,D医師の意見書については,前提事実を採用できないなどの問題はなく,専門的医学知見を踏まえて,原告の症状経過や画像等を検討の上,本件事故に,より中心性頸髄損傷を発症したと医学的に証明することは難しい旨指摘するものであって,その内容にも不合理な点はない。
(ウ)以上によれば,原告が本件事故により中心性頸髄損傷を発症したとは認められず,画像所見はもとより,神経学的所見をもって,他覚的に原告の両上肢のしびれ,頸部痛・頭痛に係る神経症状が裏付けられているなどともいえない。
そして,両上肢のしびれについては,本件事故直後に訴えがない,たとえば左右の症状経過などが一貫していると評価できるかは疑わしい,そもそも原告の主訴に相応の疑義があり,医療記録上も一貫してしびれの症状が継続していた,あるいはその改善が見られない状況が継続したとは直ちに認め難いことから,本件事故によって原告に両上肢のしびれに係る後遺障害が残存したとは認められない(ただし,これを14級9号の神経症状に係る後遺障害と判断しても,結局において,これに係る他覚的所見がないことなどから,等級評価は変わらない。)。
したがって,原告が12級の後遺障害を主張する障害のうち,頸部痛・頭痛について,14級相当の後遺障害の限度で認定する。
そうすると,原告の後遺障害は,先述のとおり,3ヶ所の14級相当の後遺障害に係る併合14級相当のものと認められる。