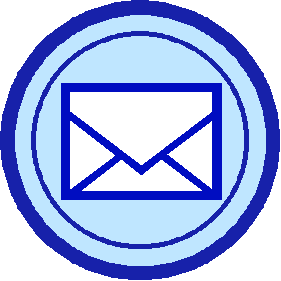就労可能期間終期についての判例変遷紹介1
○令和3年現在男子平均余命は81.47歳ですから、令和6年時の就労可能期間終期は80歳位に伸ばして然るべきと思います。しかし、裁判実務では、令和5年現在も就労可能期間終期は67歳とされています。過去の裁判例がどうなっているか見てみると以下の通り、就労可能期間終期は、令和5年からは60年前の昭和38年判決65歳、令和5年判決で67歳で、60年経て平均余命が大幅に伸びても、僅か2年しか違いません。
○令和5年の判決では、原告請求原因での主張も就労可能期間終期67歳としていますので判決もそれに従っています。これから逸失利益を請求する事件を受けたら、人生100年時代になったのだから就労可能期間終期80歳とすべきとして請求しようかと思っています(^^)。
********************************************
令和5年10月27日東京地裁判決(裁判所ウェブサイト)
第3 当裁判所の判断
1 Kの逸失利益 4494万1380円
証拠(甲12、原告C本人)及び弁論の全趣旨によれば、Kは専業主婦であったことが認められ、基礎収入は、令和元年賃金センサス女性学歴計全年齢平均を上回らない原告ら主張の388万円とした上で、生活費控除率を30%とするのが相当である。また、就労可能期間は、Kが本件事故当時31歳であったことから、36年間(対応する年5%のライプニッツ係数16.5469)とするのが相当である。
そうすると、逸失利益の額は、以下の計算式のとおりである。
【計算式】 3,880,000×16.5469×(1-0.3)=44,941,380
昭和38年7月2日宮崎地裁延岡支部判決(交通下民388頁)
理由
次に労働力の低下により喪失すべき得べかりし利益につき考察する。原告が本件事故により筋肉挫断を伴う右前腕挫創及び撓骨骨折等の傷害を蒙り治療を加えたが完全治癒に至らず右腕の機能が回復しないため、永年本職として来た鳶職ができなくなり、昭和36年頃から日給900円の工員として作業の手伝程度の労務に従事しているが、本来の鳶職がなし得た場合は日給1500円を得られる事実は既に認定したところである。そして原告の右腕の機能が将来においても回復し難い状況にあることも既に認定した事実より充分窺知できるところである。
従つて、このような原告の身体的状況、就労状況等からすれば、原告は通常の身体状況の場合に比し少くとも40パーセントの労働力の低下を来たしていることが推認される。ところで、第9回生命表によれば満60才の男子の平均余命は14年15であることは明らかであり、原告が通常の身体状況の場合には満65才までは鳶職として稼働し得ることは充分考え得るところであるから、原告が主張する昭和35年9月1日から5年間は優に右稼働期間と認めることができる。
そしてこの頃から各種職人の日給が高くなつて来たことは周知の事実であり、原告本人尋問の結果によつても延岡市方面においても鳶職の日給が1200円程度になつていたことが認められ、又名古屋市方面に出稼した後の状況も前記認定の如くであるからこの場合原告が40パーセントの労働力の低下の為失う収入額は原告が名古屋市に出稼に行く前の昭和35年9月1日以降1年間は1日金480円、名古屋市に出稼に行つてからは1日金600円と認められ、原告本人尋問の結果によれば1箇月の就労日数は25日を下ることがない事実を認め得るので、右出稼前は1箇月1万2000円、一箇年で14万4000円の、右出稼後は1箇月1万5000円、1箇年で18万円の損失額となるから、前記五箇年で合計86万4千円の損失額となる。これをホフマン式計算法により年5分の中間利息を控除すると現在において賠償を請求し得る金額は69万1200円となる。