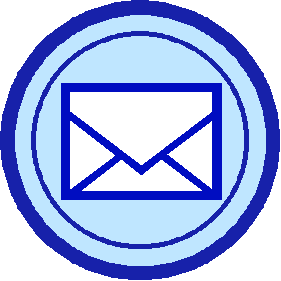30代専業主婦の67歳まで逸失利益を認めた地裁判決紹介
36歳女子専業主婦の自賠責11級7号の脊柱変形を残した後遺障害逸失利益算定につき、「一律に労働能力喪失率表の喪失率を適用することも相当ではなく」とし、腰痛が脊柱変形によらないとしても「4年が経過してもその症状が継続」している等から、12級の14%喪失が67歳まで継続すると認定した平成21年11月12日横浜地裁判決(自保ジャーナル・第1822号)関連部分を紹介します。
*******************************************
主 文
1 被告は、原告に対し、金1013万0727円及びこれに対する平成17年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その2を原告の、その3を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 請求
被告は、原告に対し、金1665万6669円及びこれに対する平成17年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
1 事案の要旨
本件は、原告が、後記の交通事故により傷害を負い、後遺障害も残ったとして、加害車両を運転していた被告に対し、民法709条に基づき、損害賠償として1665万6669円(過失相殺として20%を控除し、既払額を控除した額)とこれに対する本件事故の日である平成17年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(中略)
3 争点と当事者の主張
(1) 損害
【原告の主張】
ア 傷害慰謝料
原告は、子供が中学受験を控え、その送迎や準備等があったため、通院回数は最低限度に抑えたものであり、本来的には70日前後の通院は必要であったから、入通院慰謝料は164万円が相当である。
イ 逸失利益
(ア) 基礎収入
原告は、短大卒であり、本件事故当時は専業主婦であったが、健常であり、子育てが一段落すれば稼働しようと考えていたから、基礎収入は、賃金センサス(平成18年)女性短大卒35~39歳の平均年収417万2100円とするのが相当である。
賃金センサスについては、症状固定によって、初めて損害が具現化し、確定する以上、症状固定時を基準時とし、その年度の賃金センサスを利用すべきである。
(イ) 労働能力喪失率
原告の後遺障害は、第11級7号に該当する。そして、原告は、現実にも、後遺障害により日々の家事労働に多大な支障を来しており、毎日湿布薬をつけて痛みを和らげるべく努力しているのである。
したがって、労働能力喪失率は20%とみるのが相当である。
(ウ) 労働能力喪失期間
症状固定時の38歳から67歳までの29年間(ライプニッツ係数15.1411)
(エ) 計算方法
417万2100円×0.20×15.1411=1263万4036円
(中略)
第三 当裁判所の判断
(中略)
2 損害
(1) 傷害慰謝料
原告の傷害の程度、治療状況、入通院日数等(入院日数7日、実治療日数51日)からすれば、傷害慰謝料は135万円が相当である。
(2) 逸失利益
ア 基礎収入
原告は、本件事故当時は専業主婦であったものであり、健常で、当時小学校6年生であった長男の子育てが一段落すれば、就労したいと考えていたことは認められるが、現在の社会情勢からすれば、女性が子育ての負担が減った後に就労したいとの意欲があっても、その年代の同程度の学歴の女性の平均年収程度の収入を得られるような職に就くことは必ずしも容易ではないから、逸失利益の算定に当たって、女性短大卒35~39歳の平均年収程度の収入を得られる蓋然性があると認めることは困難であり、賃金センサス女性学歴計全年齢平均年収を基礎収入として逸失利益を算定することとする。
参照する賃金センサスの年度については、原告の症状固定が平成19年4月9日であることから、平成19年度のものを使用することとすると、その額は346万8800円となる。
イ 労働能力喪失率・喪失期間
(ア) 原告の後遺障害は、自賠責保険の後遺障害認定手続において、画像上、本件事故の外傷による明らかな第12胸椎圧迫骨折が認められ、その程度は前方椎体高の減少が後方椎体高の50%以上に至らない程度と捉えられることから、「脊柱に変形を残すもの」として、第11級7号に該当すると判断された。
(イ) 後遺障害診断書には、傷病名として、第12胸椎圧迫骨折のほかに・右膝打撲、頸椎挫傷の記載があり、自覚症状として、「後頭部に冷たい風があたるとピリピリする」「頸周囲に常に軽い痛み」「左肩甲骨周囲が一番痛い」「背中の中心もたまに痛い」「腰尾骨部痛は常にある」「右膝痛常に」「左足底の感覚異常と歩行時痛」との記載がある。
自賠責保険の事前認定においては、これらの症状について、医証上、受傷当初のA病院では、頸部に関する受傷、右膝部に関する受傷、腰部及び右足底に関する受傷は認められておらず、本件事故から52日後のB病院において、頸部挫傷、右膝打撲と記載されていることから、症状と本件事故との間に相当因果関係は認め難いとして、自賠責保険の後遺障害には該当しないと判断されている。
しかし、Cクリニックの外来カルテを見ると、平成17年10月11日の初診時、「右膝は靭帯損傷半月板損傷を疑う所見」などと記載されており、丙川三郎医師がこれを本件事故によるものとみていることは明らかであり、本件事故後に別の原因で右膝打撲や頸椎挫傷の傷害を負ったことをうかがわせるような事実もないのであるから、右膝打撲、頸椎挫傷についても、本件事故によるものと認めるのが合理的と思われる。
もっとも、右膝打撲、頸椎捻挫による後遺障害があったとしても、それだけでは原告の主張する20%の労働能力の喪失が生じるとは通常は認められないから、労働能力喪失率については、第11級7号に該当すると判断された脊柱の変形によるものが主として問題となると考えられる。
(ウ) 上記のとおり、原告は、画像上、明らかな第12胸椎圧迫骨折が認められたことから、第11級7号に該当するとされたものであり、労働能力喪失率表に従うと20%の労働能力の喪失があることになる。
ところで、脊椎圧迫骨折後の変形(第11級)については、労働能力の実質的喪失を否定する見解や、第12級に引き下げるのが妥当であるとの見解もあり、障害等級の位置づけについての専門家による検討もされているところであるが、現時点においてもその変更はされていないことからすれば、原則としては、労働能力喪失率表の定める喪失率を認めるのが相当であると考えられる。
もっとも、骨折による変形が軽微であり、労働能力への制約がそれほどないという場合もあるので、一律に労働能力喪失率表の喪失率を適用することも相当ではなく、変形の部位・程度、現在の症状の原因、被害者の年齢・職業等から、具体的事案に即して労働能力喪失の程度を判断すべきものと考えられる。
(エ) B病院リハビリテーション科のカルテには、理学療法士による報告が記載されているが、平成18年4月3日の記載を見ると、「腰はしびれとかはないのですが、何となく重い感じがあります。」との原告の訴えの記載があり、腰痛の原因について、「腰背部に筋筋膜性の腰痛あり腰痛の原因は圧迫骨折によるものではなく、筋筋膜性の腰痛であると考える。」「一旦リハビリは終了し、再度自宅訓練を継続していただき経過観察していただく」との記載があり、理学療法士は、原告の腰痛について、第12胸椎圧迫骨折によるものではなく、筋・筋膜性腰痛であるとみている。
原告は、陳述書において、Cクリニック整形外科の丙川三郎医師から、平成19年4月ころ、「あなたの場合、筋肉の細胞に細かい傷がついていて、これが治らないから、これ以上通院してもあまり役に立たないですよ。」ということを言われたと述べ、本人尋問においても同様のことを述べている。
そして、同医師が原告に対してそのような説明をしたという事実は、同医師が、原告の腰痛について、筋・筋膜性腰痛であるとみていることを示すものである。
(オ) 丁山四郎医師は、F会社作成名義の意見書において、原告の圧迫骨折について、圧迫骨折の程度は軽微であり、圧縮率は椎体後壁高が28㍉㍍に対し、前壁が25㍉㍍程度であり、80%以上となっていることから、実際上ほとんど後弯変形はないとみてよく、受傷当初は強い痛みがあったことは否定しないが、骨癒合さえすれば普通は痛みが残らない程度の変形であるとする。そして、「腰の重い感じはむしろ、過重な安静により筋肉や動きが衰えたためと思われる。元の生活に戻ることが遅れ、十分な運動療法が見られないときに遺残することが多いが、逆に積極的な運動療法によって改善しうる。」とする。
前記のとおり、原告の治療に当たっていたCクリニック、B病院の医師、理学療法士も、原告の腰痛について、第12胸椎圧迫骨折によるものではなく、筋・筋膜性腰痛であるとみており、丁山医師の前記見解も相応の合理性を有するものといえる。
(カ) そうしてみると、原告の腰背部の疼痛の訴えについては、誇張があるわけではなく、原告が述べるとおりの疼痛があるものと認められるものの、圧迫骨折による脊柱の変形を原因とするものとは認められないから、脊柱の変形により第11級7号に該当することから、直ちに労働能力喪失率を20%と認定することは相当ではないと思われる。
もっとも、原告の腰痛が脊柱の変形を原因とするものではないとはいっても、本件事故との相当因果関係がそのことによって否定されるわけではなく、証拠(略)によれば、事故から4年が経過してもその症状がなお継続し、家事労働や日常生活に支障が生じていることが認められることからすれば、労働能力喪失率を第14級程度の5%とし、労働能力喪失期間を数年間とみることも相当とは言い難い。
以上のような事情を総合すると、労働能力喪失率を第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と同等の14%とし、労働能力喪失期間を症状固定時の38歳から67歳までの29年間とみて、逸失利益を算定するのが相当であると判断する。
ウ 逸失利益算定における中間利息の控除の基準時
この問題については、事故時を基準として中間利息を控除するという説も理論的には成り立つが、後遺障害による損害の具体的な発生時期は症状固定時であるから、症状固定時を基準に逸失利益を算定する方が自然で簡明であり、基準時を症状固定時とすると、事故時から症状固定時まで遅延損害金が付されるのに、中間利息の控除においてはこの期間を考慮しないことになるが、遅延損害金は単利で計算されるのに対して、中間利息はライプニッツ方式では複利で計算されるので、事故時から症状固定時までの中間利息が控除されないことが直ちに不公平であるとまではいえない。
したがって、事故から症状固定までに極めて長期間を要したような場合はともかくとして、原則的には、症状固定時を中間利息控除の基準時とするのが相当である。本件の場合、事故から症状固定までは1年7ヶ月強程度であるから、症状固定時を中間利息控除の基準時としても不合理ではなく、症状固定時を基準時として逸失利益を算定するのが相当である。
エ そうすると、以下の計算式により、逸失利益は、735万3002円(1円未満切り捨て)となる。
346万8800円×0.14×15.1411=735万3002円
(3) 争いのない損害と上記(1)、(2)を合計すると、1346万3582円となる。